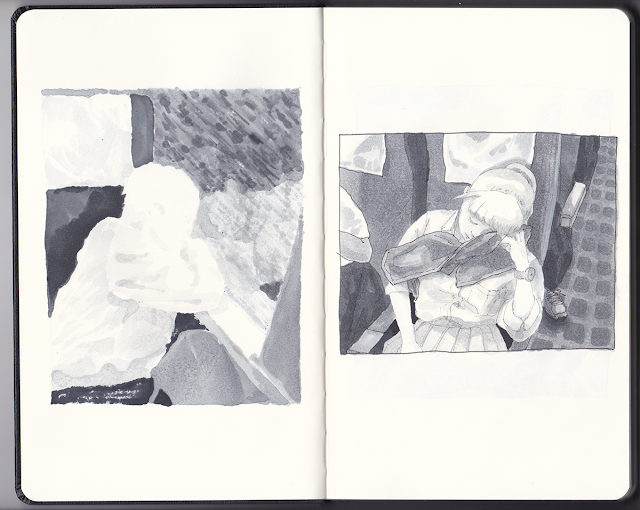弾丸で、福島にある諸橋近代美術館に行ってきた。
「ととのう展——ヘルスケアにつながる美術館」という企画展の、マインドフルネス関連のパネルを関西大学の小室先生が監修していると聞き、見に行くことにしたのだった。
車で行ってみたら高速使っても片道3時間半で、思ったよりも遠かった。
帰り道、栃木らへんで最高速度120km/hの区間があった。普段使う高速道路は最高速度100km/hなので、さらに20km速く走って良いわけである。三車線の真ん中を怖気付いて100km/h前後のまま走っていると後ろからくる車にどんどん追い越されるので、自分も120km/h出してみることにした。
感想は「意識した側から過去になっている」である。ああ、もうすぐカーブだから少し体を傾けるかと思った時にはもうカーブを通り過ぎているみたいな……。どうやってカーブを曲がり切ったのか、認識する前に通り過ぎて思い出せないのだ。動体視力が追いつかない。新幹線の運転手はこの倍以上のスピードで走るのだからとんでもないことだと思った。
120km/h出すのは少し頑張ってみて、すぐやめた。心臓が知らない痛みを訴えていた。
そして、今の自分が実感を持って走れるのは大体98km/hくらいだと理解した。下り坂で100km超えてはまた90km後半になるくらいが自分の身の丈に合っている。
120km/h区間が終わり、さらに少し行くと少し道が狭くなって、気づいたら80km/hで走っていた。流石に遅すぎるかと思って標識を見ると80と書いてあって、適当だったことがわかった。こういうことがよくある。なんとなく40km/hで走っていると実際40km制限の標識が立っていたり、ここは60km出せるなと思ったら標識に60と書いてあるのが見えたりといった具合だ。そういう時、国の道に対する見解と自分の実感が一致しているなと思う。